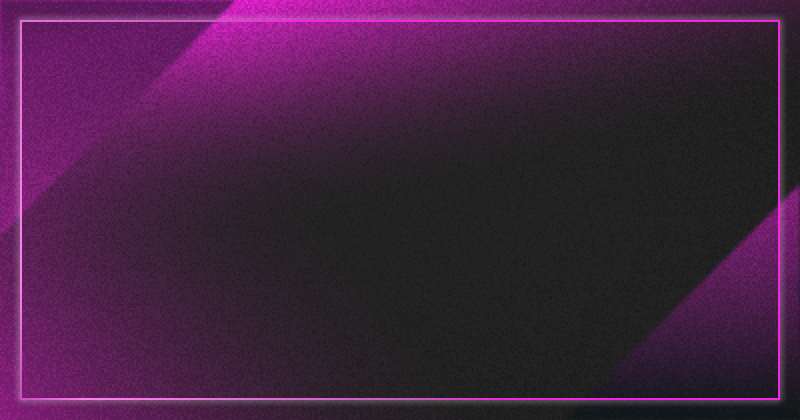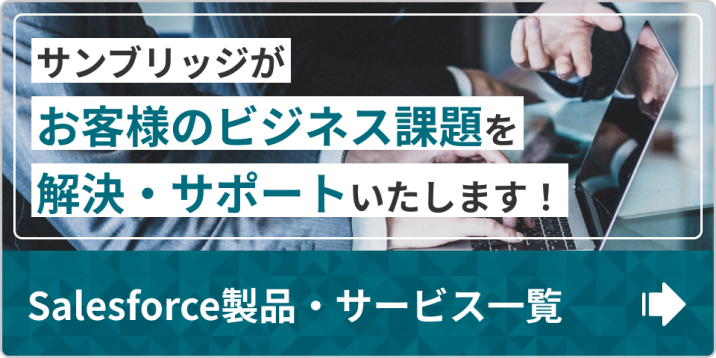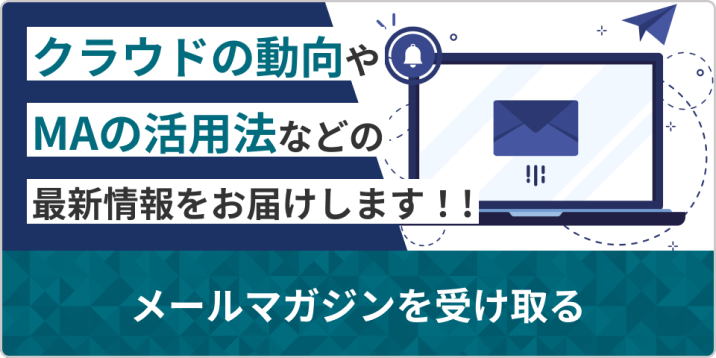展示会には多くの来場者が訪れるけれど、期待したほどリード(見込み客)を獲得できないまま展示会が終わってしまった…とお悩みの営業・マーケティングの方も多いのではないでしょうか。
また、獲得したリードに対して最適な施策を打つことができず商談化しにくかったり、見込みが高くないと判断したリードにはフォローせず放置したままになってしまっているといった場合もあることでしょう。
そこで本記事では、展示会出展で新規リードの獲得数を増やすために重要なポイントや、獲得した名刺や顧客データを有効活用して商談・受注につなげる方法についてご紹介いたします。
そもそも展示会に出展するメリットとは?
獲得できる新規リードの層を大幅に広げることができる
企業のマーケティング部門にとって、自社製品やサービスのニーズがある新規リードをどんどん獲得し、営業に引き渡す施策として展示会への出展は非常に効果的です。Webサイトや広告出稿だけでは接触できない新規リードを獲得することができるので、顧客データを充実させる良い方法です。
見込み客と直接対話し製品やサービスの良さをしっかり伝えられる
ブースで実際の製品やデモンストレーションを見せながら競合他社との差別化や興味醸成をはかることができ、Webサイトや資料だけでは伝えづらいような製品の手触りや操作感、動作の様子を体感してもらうことができます。
企業ブランディングやクロスセル・アップセルにも役立つ
会社や商品の認知度を上げるブランディングとしても効果を発揮するほか、来場者のなかには自社の既存顧客も存在するため、最新の情報を提供して関係構築をし、クロスセルやアップセルといった商談が生まれるといったメリットもあります。
展示会に来場するリード(見込み客)の特徴
来場者の75%はまだ情報収集の段階
リードの購買行動における最初のステップとして、複数ある製品・サービスのなかから「比較検討」を行いますが、展示会で獲得したリードの75%はこの「情報収集・比較検討段階」と言われています。この情報収集の期間に顧客が求める情報を提供し、自社のサービス・商品に興味を持ってもらうかがビジネスの成否を握る大きなポイントになります。
この段階で見込客を放置していると、積極的アプローチを行っている企業、たとえばMA(マーケティングオートメーション)ツールを用いたセグメントアプローチや、定期的なメール配信を通した興味関心の醸成などを行っている競合他社のサービス・商品に顧客を奪われることにもなりえます。
いますぐ商談にならなかったリードも放置してしまうのではなく、効率的かつ効果的にフォローし商談機会を創出することは営業・マーケティング部門にとって大きな課題と言えるでしょう。
展示会出展で獲得するリードを増やすために重要な点
展示会に1回出展するだけでも大きなコストと労力がかかる展示会だからこそ、1人でも多くの来場者と名刺交換をし、リード獲得につなげたいものです。ここでは、リード獲得に必要な施策をチェックしてみましょう。
出展ブースは人通りの多いところを確保する
ブースを出展する場所によってもリード獲得数に差が出るため、出展申し込みの時点で可能な限り会場の出入り口付近や、会場内のメインの通りに面したブースを確保することをおすすめします。会場内の中央がメインの通りとなりますが、展示会によってはブースの指定ができない場合もありますので、事前に展示会運営会社に確認と交渉を行うことを意識しましょう。
混雑する時間帯や開催日を把握し人員配置を整える
多くの展示会では、午前10時から午後18時くらいまでの時間で数日間にわたり開催されます。このうち、来場者が多く訪れるピークの時間帯は午後13~16時頃、開催初日よりも2日目・3日目のほうが多いといった傾向もみられます。この時間帯は人員を多めに配置したり、営業アプローチの上手いスタッフは必須で配置することで、リードに対応しきれず機会損失になってしまうといったことを防ぐことができます。来場者の多い時間帯や開催日は展示会運営会社が教えてくれる場合があるので、事前に確認してみると良いでしょう。
自社ハウスリストへのメール配信やWebサイト掲載で集客数を増やす
ハウスリストとは、過去に名刺交換やイベント、Webサイトのお問い合わせフォームなどを経由して蓄積した、自社で保有する顧客情報のことです。 これらの顧客データはすでに自社データベースに存在するため新規リードの獲得にはなりませんが、展示会に来場するメリットをメールで配信することにより、ニーズのあるリードが来場しやすくなります。 メールでの配信はもちろん、自社サイトのニュースページやイベントページに掲載するなどして、メールを見逃した方でも情報をキャッチできるようにすると良いでしょう。
来場者にとってのメリットを設ける
自社のブースに立ち寄った来場者に御礼として製品のサンプルを渡したり、ロゴが入った文房具をプレゼントするなどのメリットを用意しましょう。 そうした物品の提供以外にも、サービスの割引や特典を用意することで、競合他社と比較している顕在リードとの商談を有利に進められるようになります。
来場者が求める情報があることをパネルやポスターなどで判りやすく伝える
製品やサービスの種類や特徴、上記でご紹介したようなメリットをポスターやスタンドバナーなどで掲示することで、有益な情報があることを伝えることができ、通りすがりのリードが立ち寄りやすくなります。多くのリードがあらかじめ立ち寄るブースに目星をつけて来場しますが、ブースを回り歩いている時に自分が探している製品やサービス内容を見て「ちょっと見てみようかな」と足を止めてもらうことを狙いましょう。このとき、掲示物が来場者がパッと見て理解できるようにするため、文字を大きめ・少なめにすること、インパクトを持たせることを意識しましょう。
デモやアンケートなどを行い、リードがブースに立ち寄りやすくする
ブース内にスタッフが大勢いたり、他の来場者がいないようなブースでは、なんとなく入りづらく見えてしまい、来場者はブースを避けて通るようになってしまいます。 そこで、デモ(実演)やアンケートなどをすることで立ち寄ってもらいやすくしたり、ブースの入り口付近を広くとって解放感をもたせることで、来場者が立ち寄りやすい雰囲気を作ることができます。
また、展示会が始まってからも来場者の反応に合わせて人員配置やトークスクリプトを見直し、機会損失になっているポイントは無いか、来場者が興味を示したスクリプトはどのようなものだったのかをスタッフ間でこまめに共有し、すぐに改善するようにしましょう。
展示会で獲得したリードにアプローチするまでのプロセス
展示会が終了したあとには、獲得したリードの見込度や温度感に合わせていかに最適なアプローチができるかが商談化を生み出す分岐点となります。実際の名刺の仕分けから管理、具体的なアプローチの方法までを見ていきましょう。
名刺のデジタル化と一元管理
まずは、展示会で獲得した名刺はすぐに名刺管理ツールなどを用いてデジタル化し、担当者ごとにバラバラに管理するのではなく社内で共有・一元管理することが重要です。 名刺管理ツールとは、名刺に記載された部署や役職などの顧客データをクラウド上に保存管理して、社内で共有・活用するための充実した機能が備わっているアプリケーションです。業務のDX化が推し進められている昨今において、名刺管理ツールを既に利用している企業も多いことでしょう。
スマートフォンのカメラなどで名刺を撮影・スキャンするだけで、簡単に顧客情報をデータとして取り込めるため、名刺交換をした顧客情報を管理するのに最適です。手入力で名刺を登録する工数を大きく削減し、すぐにアプローチを開始することも可能になります。
名刺管理ツールのなかには、弊社が提供する「SmartVisca(スマートビスカ)」のように、社内で名刺情報を共有できたり、見込客とつながりのある社内の人物を可視化し営業活動に役立てたり、蓄積したデータから顧客リストを手軽に作成するといった機能を備えたものもあります。
従来、人脈や顧客接点の情報は経験を積んだ営業マンが地道な活動を経て頭のなかにだけしまいこんで属人的な営業になりがちだったり、リストを作成するにも膨大な時間と手間、そして入力ミスの修正など非効率な作業を伴うものでした。データを蓄積・活用することでこれらの作業をものの数分で完了できるようになり、誰でも人脈や顧客接点を営業に活かせるようになります。
ホットリードの選別にはランク分けがおすすめ
ホットリードとは「契約・購買に至る可能性が高い見込客」を意味するマーケティング用語です。昨今のデジタル化推進やマーケティングオートメーション(以下MA)ツールの普及などで、よりホットリードの選別の重要性が高まってきました。
まずは、展示会場でリードと交わした会話をもとに、以下のようなランク分けをすると良いでしょう。
ランクA:「詳しく話を聞きたい」「いま製品やサービスの比較検討中」と明確なニーズがあるリード
ランクB:「資料が欲しい」「事例を知りたい」など興味を示したリード
ランクC:まだ製品やサービスを利用するかどうかも未定のリード
ランクD:学生や競合、パートナー企業など顧客にはならないリード
前述のように獲得したリードの75%は情報収集段階と言われており、それが「ランクC」のリードに該当します。獲得したリードのすべてがすぐ商談化するわけではないため、情報収集の段階から商談化率や成約率を高めていくためには、顧客のナーチャリング(育成)で契約・購買に至る確度を高めていき、ホットリードになった最適なタイミングでアプローチを仕掛ける必要があります。
お礼メールで継続フォロー
顧客データをきちんとデジタル化しておくことで、メールアプローチを素早く仕掛けることが可能になります。そこで展示会でご挨拶したことに対する「お礼メール」を送信すると良いでしょう。
展示会の場で名刺交換を行い、サービス・商品に関する簡単に説明して、その後に先方側から興味を持って連絡をもらえるパターンはごく稀と言えます。たとえば、展示会の場で行った顧客へのヒアリングを基に、さらなる詳細資料やWebページのリンクといった追加の情報をお礼と併せてメールで送付し、仮に自社のサービス・商品が相手側の課題解決になることを訴求できれば、顧客の具体的なアクションを促せることができます。
商談や契約に至らなかった顧客データの活用方法
展示会に出展した企業の多くが獲得したリードに対して直後からアプローチを仕掛けているものの、商談に至らなかったリードや情報収集段階のリードに関しては継続的なフォローをせず放置しているケースが多いと言われています。
では、こういった商談に至らなかった「コールドリード」をどのように活用すれば良いのでしょうか。 ここではその方法について解説します。大まかには以下の2点が重要になります。
失注の原因分析を行う
なぜ商談に結びつけられなかったのか、なぜ失注したのか、その原因を徹底分析することは非常に重要であるものの、そこまで手が回っていないという企業も多いことでしょう。
そもそも商談にならなかったのであれば、なぜ興味を持ってもらえなかったのか、なぜ商談や契約に至らなかったのかを適切に評価分析できていなければ、アプローチを仕掛け直したところで、再び失敗する可能性が高くなります。
そうならないためにも、商談や契約に至らなかった顧客リストから特徴や傾向を分析し、そのナレッジを蓄積していくことが重要です。特に顧客のデータが多ければ多いほど傾向が現れやすくなります。
掘り起こしを行う
契約・購買までに至らなかった理由として、顧客の購買ニーズが高くなかった可能性が大いにあります。原因分析を行い、定期的に顧客の意思を確認する上でもリードの掘り起こしを行うと良いでしょう。
掘り起こしのメリットは、新規の営業と比較して商談につなげやすいという点です。展示会を通して一度は、自社のサービス・商品を紹介しているため、全く認知されていない状態から新たに顧客と関係性を構築する必要性はありません。
また、リード獲得のための費用がかからない点も大きなメリットです。展示会への出展は大きなコストがかかるため、1回の出展でできるだけ多くの新規リードを獲得する必要があります。一方、掘り起こしの場合はすでにリード情報を保持している状態で、営業活動をスタートできるためコスパの良い施策と言えます。
具体的には、休眠顧客に対して興味がありそうな情報事項をまとめたメールを一斉送信し、その反応を顧客ごとに分析、選別するなどして、徐々に自社のサービス・商品に興味を持ってもらうように継続してリードナーチャリング(顧客の育成・興味醸成)をすると良いでしょう。 リードナーチャリングの概要と方法については以下の記事で詳しく解説しています。
▼リードナーチャリングとは
https://www.sunbridge.com/blog/dictionary/lead_nurturing/
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では、展示会で獲得するリードを増やす方法と、展示会後のアプローチのプロセス、名刺や顧客データの活用方法についてご紹介いたしました。
せっかく獲得できた顧客データを放置することなく、顧客一人ひとりに最適化したフォローを展示会後にすぐ行うことで、リードの不足や商談・受注率を改善でき、今後のビジネスを優位に進めることにつながります。
展示会出展するなら必見!
商談創出に差がつく名刺管理ならSmartVisca!

展示会に出展する企業様に多くご利用いただいている名刺管理「SmartVisca(スマートビスカ)では、大量の名刺でも取り込み制限を気にせず一気に取り込むことができます。取り込んだ名刺は約1分でデジタル化され、すぐに御礼メールの配信や営業アプローチを開始し、いち早く商談につなげられます。